気象予報士を目指すあなたへ!このページでは、X(旧Twitter)で毎日投稿している「#デミークイズ」をまとめて掲載しています。過去の問題を復習したいとき、解説を読みたいときにご活用ください。
デミークイズとは?!
「デミークイズ」は、気象予報士を目指す皆さんのために出題している○×形式の学習クイズです。試験によく出る基礎知識や、ひっかけやすいポイントを楽しく学べるように、気象予報士アカデミーの講師・デミー先生が日替わりで問題をお届けしています。
SNS(X/旧Twitter)で週3回配信され、ここでは過去の問題と解説を一覧で振り返ることができます。日々の復習や、スキマ時間の学習にぜひご活用ください。
| 📱 スマホで毎朝チェック! デミー先生のクイズはXで毎日更新中♪ → @yohoushiac をフォローして一緒に楽しく学ぼう! |
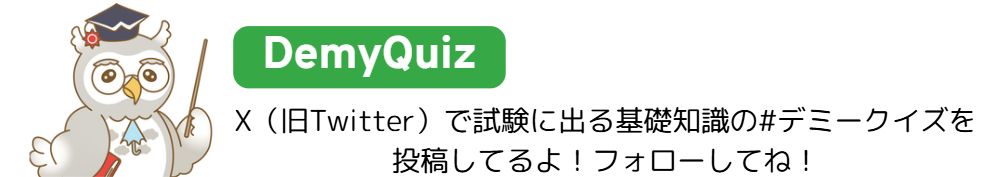
デミークイズ一覧(これからどんどん更新していくよ!)
×波長の4乗に反比例する。ちなみに、青い光は赤い光の約9倍も強く散乱される よく出る基礎問題。間違えた人はこちらで勉強しよう!
×周囲の空気の気温減率が、乾燥断熱減率よりも小さく、湿潤断熱減率よりも大きい場合です。
×高気圧とは、周囲よりも気圧が高く、閉じた等圧線で囲まれたところをいいます。そのため、気圧が○○hPa以上であれば高気圧というわけではありません。相対的に周囲より気圧が高いかどうかで判断されます。間違えた人はこちら
×温度は変わらないけど、姿が変わるときの熱は潜熱、温度が変化し、温度計で変化が測れるのは顕熱。間違えた人はこちらで勉強!
×バックビルディング現象は、積乱雲が自分の後ろ(風上)に新しい積乱雲を次々と作り出し、その場に居座り続けることで、記録的な大雨をもたらす現象のこと。間違えた人はこちらで勉強
× ×虹は光の「分散」によって生じる。彩雲は光の「回折」によって生じる。回折ってなに?はこちらで勉強
〇絶対不安定とは周囲の空気の気温減率が、乾燥断熱減率よりも大きい場合です。空気が少し持ち上げられただけでも、自発的にどんどん上昇していくので、積乱雲が発達しやすく、激しい雨や雷雨、竜巻などの激しい気象現象が発生しやすい状態。もっと勉強するならこちら
×太実線は 20hPaごと、細実線は 4hPaごとです。 図解と練習問題はこちら
×線状降水帯が発生・持続する場合、下層と上層の風向は基本的に「異なる」ことが多いです。 特に重要なのは、下層の暖湿気流が一定方向から持続的に流れ込む一方で、上層では異なる方向の風で、積乱雲の上部を吹き流すような形になることです。線状降水帯をもっと勉強しよう
〇一般的に高度が高くなると共に気圧傾度が大きくなるので、地衡風も高度が高くなるほど強くなる。ロジックもちゃんと理解しよう
Aドボラック法とは、「気象衛星画像から台風の雲の形や構造を分析して、その強さ(中心気圧や最大風速)を推定する手法」のこと。衛星画像だけで強さを見積もれるよ。間違えた人はこちらで勉強!
×アジアモンスーンは存在するモンスーンの中でももっとも大きいと言われ、水平スケールで1万kmほどです。傾圧不安定波よりもはるかに大きく、超長波と呼ばれるプラネタリー派と同じくらいです。
×温度風ベクトルの右側が暖域、左側が寒域。温度風ってなんだ?実際の風じゃないってなんだ?というひとはこちら
〇表面張力によって水滴の中の水が内側から外に押し出される力が大きくなるので、飽和水蒸気圧が大きくなるんです。気象予報士試験でも、度々関連した問題が出題されていますので、受験を予定されている方はしっかり理解しておくようにしましょう!
×「光電離」は「熱圏」で起こります。「成層圏」で起こるのは「光解離」。光電離と光解離は、どちらも紫外線と大気分子・原子による反応であり、共通点もありますが、様々な要素に違いがあるよ。ちゃんと違いを勉強してね。
現在、2025年8月試験対策模擬試験お申し込み受付中!
「やっておけばよかった」と後悔しないために
気象予報士専門講師による本番形式の実戦チェック、今すぐ始めましょう。
模擬試験をはじめ、受講を迷ってる方、ぜひLINEで相談してください!
