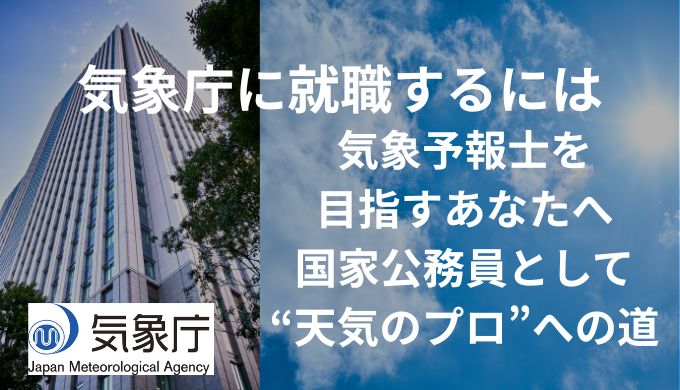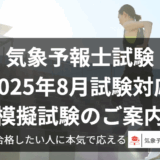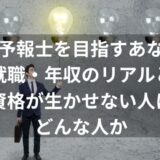気象予報士を目指す方にとって、気象を専門に扱う国家機関である「気象庁で働く」ことは、一つの大きな夢であり、憧れの進路かもしれません。
防災、気候変動対応、航空や海上の安全まで──天気に関わるあらゆる分野の最前線で活躍する“天気のプロ集団”が気象庁です。
では、どうすればその一員になれるのでしょうか?
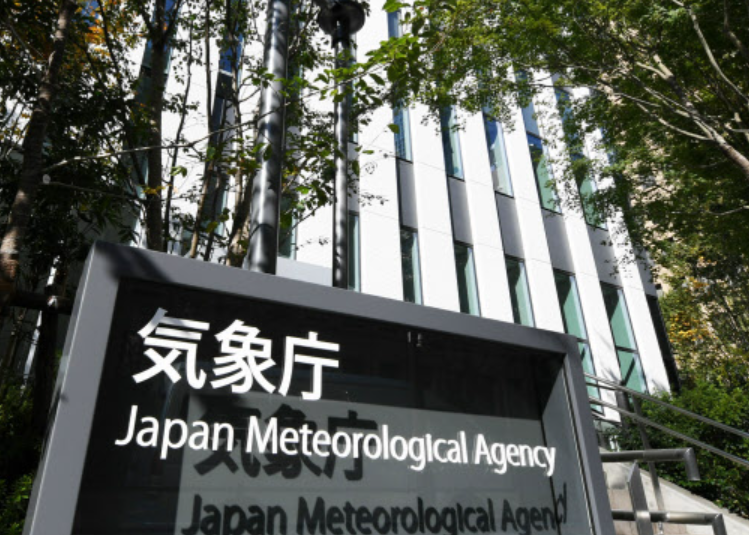
本記事では、これから気象予報士試験の勉強をスタートしようとしているあなたに向けて、
- 気象庁に就職するための3つのルート
- 必要な学歴・年齢・試験ステップ
- 気象予報士資格がどう役立つか
- どんなキャリアが描けるのか
- 気になる給与・福利厚生の実態
を具体的に丁寧に解説します。
未来の自分をイメージしながら、ぜひ最後まで読んでみてください。
気象庁で働くには?必要な3つのルートを解説
気象庁で働くには、国家公務員試験を経て採用される必要があります。以下の3つのルートが存在します。
◆ ① 総合職ルート(政策・企画・本庁勤務が中心)
対象:大学卒業程度(4年制大学卒業または同等の学力を有する者)原則、21歳以上30歳未満(例年4月1日時点)
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 試験申込 | 毎年3月上旬〜下旬に人事院サイトで出願(国家総合職) |
| 第一次試験 | 4月上旬:教養+専門(数理・物理・法律等)+論文 |
| 第二次試験 | 6月上旬:人物試験(面接) |
| 官庁訪問 | 6月中旬〜下旬:気象庁の人事課と個別面接(複数回) |
| 内々定 | 7月中旬、採用通知を経て翌年4月入庁 |
◎ 採用人数は毎年5~10名ほど。国際業務・管理職候補などが中心で、本庁配属が多いです。

◆ ② 一般職ルート(地方気象台・観測現場中心)
対象:大学卒業程度(4年制大学卒業または同等の学力を有する者)原則、21歳以上30歳未満(例年4月1日時点)
| ステップ | 内容 |
| 試験申込 | 毎年4月上旬~下旬(人事院サイトから) |
| 第一次試験 | 6月中旬:教養+専門(地学・物理など) |
| 合格発表 | 7月中旬 |
| 官庁訪問 | 7月下旬〜8月上旬:気象庁と面接(複数回) |
| 採用・配属 | 8月下旬内々定、翌年4月入庁 |

◎ 採用人数は10名前後。全国の気象台・空港支所・海洋観測所などに配属され、観測・予報・防災業務を担います。
◆ ③ 気象大学校ルート(高卒者向けのエリート養成)
対象:高等学校卒業(または見込み)
| ステップ | 内容 |
| 試験申込 | 毎年8月下旬〜9月上旬(高卒程度試験) |
| 第一次試験 | 10月下旬:基礎能力+適性試験 |
| 第二次試験 | 12月中旬:人物試験(面接)+身体検査 |
| 合格発表 | 翌年1月中旬 |
| 入学 | 翌年4月、気象大学校(埼玉県久喜市)に4年間在学 |

◎ 合格者は在学中から国家公務員(行政職)として給与が支給され、寮完備・授業料無料。卒業後は全国の気象台に配属。
気象予報士資格は必要か?
いずれのルートでも、気象予報士資格は受験の必須条件ではありません。 しかし、入庁後の予報現場では実際に予報業務に携わります。そのため、気象予報士試験で学んだ専門知識は、現場でのデータ解析や予測判断、説明資料作成などに直結し、入庁後の即戦力として重宝されるケースも多く、気象予報士資格の取得はキャリア形成においても大きな武器になります。
気象予報士資格を取るメリット
- 試験・面接での強力なアピール材料になる
- 配属後、予報官・解説官として昇進しやすくなる(知識があるため、習得が早い)
- 気象大学校や研修での理解がスムーズ
気象庁でのキャリアと働き方
近年は女性職員の登用も進んでおり、育児と両立しながら第一線で活躍する例も多く見られます。
| 年次 | キャリア例 |
| 1〜3年目 | 地方気象台や空港支所での観測・通報・気象データの整理・報告など |
| 4〜6年目 | 気象予報官として数値予報を基にした短期・中期予報、防災対応、住民への解説を担当 |
| 7〜10年目 | 技術系や管理系ポジションへ異動。防災・気象情報の調整や、自治体との連携業務も経験 |
| 10年目〜 | 本庁勤務(国際業務・政策企画など)や、海外派遣、研究機関との連携など |
| 15年目〜 | 課長補佐・課長・地方台長などの管理職ポスト、または内閣府・外務省などへ出向あり |

国家公務員として、安定した待遇と充実した福利厚生
気象庁職員は、国家公務員としての身分が保障されており、安定した収入と充実した福利厚生制度が整っています。全国各地に勤務することになりますが、その分、手当や支援制度がしっかりと設けられており、安心して長く働き続けることが可能です。
◆ 給与・手当
- 初任給:約21万〜24万円(学歴・職種・勤務地により異なる)
例:大卒・一般職で約22万円前後からのスタート。採用区分や職務内容によって異なります。 - 年2回(6月・12月)支給され、年間支給額は給与の約4.4ヶ月分(令和6年度実績)
- 地域手当:勤務地に応じて最大20%加算
- 例:東京都特別区内に勤務する場合、基本給の20%が加算されます(例:22万円 × 1.2 = 約26.4万円)
- 通勤手当:上限ありで全額支給
- 公共交通機関で通勤する場合、その費用は全額支給されます(上限あり)
- 住居手当:最大28,000円
- 賃貸住宅に住む職員に対して支給される手当です。公務員宿舎に入居しない場合に活用されます。
- 扶養手当:配偶者や子ども等がいる場合に支給
- 家族構成に応じて手当が加算されるため、子育て世代にも安心の制度です。
賞与(年2回)、年次有給休暇や特別休暇、共済組合(年金・医療制度)、転勤時の職員宿舎利用など、生活面でもしっかりと支えられる仕組みが整っています。気象庁は長期的なキャリア形成を視野に入れながら、働く人の暮らしと人生設計を大切にする職場です。
◆ 年収モデル
- 20代後半(一般職):約400万〜450万円
- 30代後半〜40代(予報官クラス):約550万〜700万円
- 管理職クラス(本庁課長補佐〜課長級):700万〜900万円以上
◆ 休暇制度
- 年次有給休暇:年20日(繰り越し最大40日)
- 夏季休暇:原則5日
- 特別休暇:結婚・出産・忌引き・ボランティア等
- 産前産後休暇/育児休業:取得実績多数、男性職員の育休取得も促進中
◆ その他制度
- 共済組合:国家公務員共済組合に加入(健康保険・年金)
- 職員宿舎:転勤時の住宅支援あり、単身者・世帯用ともに用意
- 研修制度:気象庁研修所での専門教育、海外研修や国際会議派遣もあり
- 自己啓発支援:通信教育補助、語学・資格取得費用一部補助
◆ 働き方改革への対応
- フレックスタイム制やテレワーク制度の試行・導入も進行中(部署による)
- 時差出勤、育児時短勤務制度などライフステージに応じた柔軟な勤務も可能
これらの制度により、長期的に安心して働きながらスキルアップや家庭との両立がしやすい環境が整備されています。
※記載している年収や制度の情報は随時更新されますので、最新の情報は気象庁の募集ページ等で確認して下さい。
まとめ:国家の防災・安全を支える気象庁の仕事へ
気象庁で働くということは、単なる職業を超えて、社会の安全と安心を守る責任ある使命です。
国家公務員試験という壁はありますが、しっかり準備すれば必ず突破できるものです。そして、気象予報士資格はその突破力を強め、配属後の活躍の場も大きく広がります。
実際に気象予報士アカデミー受講生も「しっかりとした講座を受講しながら資格取得の勉強をしている」という点をPRして、資格取得前でしたが、気象庁に転職できました。
今、あなたの選択が未来を変えます。気象を学び、国を支える専門家として羽ばたきましょう
「気象予報士の資格は取りたいけど、どのように勉強すれば良いのかわからない」
「テキストを買ってみたけれど、わからないことだらけ…」
「一人で受験勉強をする自信がない」
などなど、一人で悩んでいませんか?
気象予報士アカデミーでは、LINEでの受講相談を受け付けております。
友達登録していただいた方には、3分でわかる気象予報士合格ポイント動画をプレゼント!
ぜひご登録ください。
\ 講座へのご質問はお気軽に! /