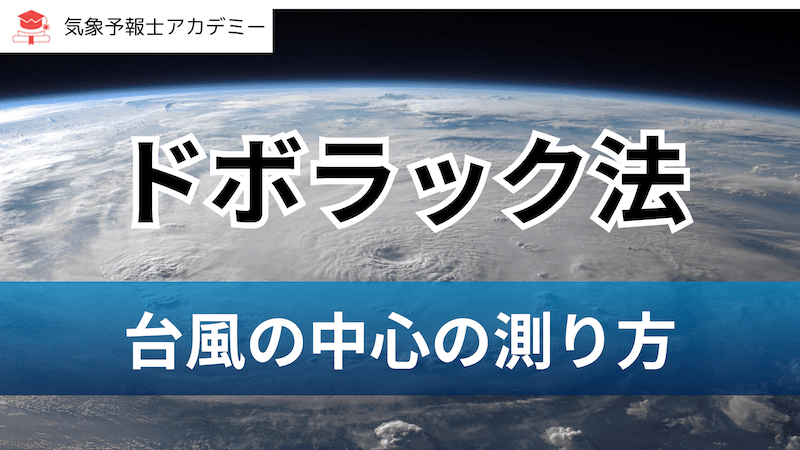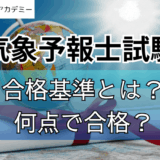台風の中心気圧ってどうやって測ってるんですか?

ドボラック法を使って導き出しています。
詳しく説明しますね。
テレビやインターネットで台風のニュースを見ていると、「中心気圧は〇〇ヘクトパスカル」といった情報が必ず出てきますよね。
でも、広大な海上を進む台風の、それも一番勢力が強い中心部分にどうやって測りに行くんだろう?と疑問に思ったことはありませんか?
実は、気象機関がこの気圧を直接測ることはできません。
代わりに、とても巧妙な「裏技」が使われているんです。
それが、今回ご紹介する「ドボラック法」です。
※この記事は、当講座に在籍する気象予報士が監修しております。
ドボラック法とは?
ドボラック法とは、「気象衛星画像から台風の雲の形や構造を分析して、その強さ(中心気圧や最大風速)を推定する手法」のこと。
衛星画像だけで強さを見積もれる。
ドボラック法(Dvorak technique)は、気象衛星画像から熱帯低気圧(台風やハリケーンなど)の勢力(中心気圧や最大風速)を推定するための解析手法です。
アメリカの気象学者バージニア・ドボラック氏によって1970年代に考案され、現在でも世界中の気象機関で広く用いられています。
ドボラック法とは、気象衛星画像(特に赤外画像)を用いて、台風の雲構造や発達の程度から強さ(中心気圧や最大風速)を推定する手法です。
この方法では、台風の「クラウドパターン」(雲の形状や渦の巻き方、眼の有無など)を定性的に評価し、それに応じて「Tナンバー(T値)※1」を割り当てます。
Tナンバーと台風の強度(中心気圧や風速)との関係が経験的に定められており、これにより数値的な推定が可能となります。
特徴は以下の通りです:
- 観測機器が現地にない海上でも、台風の強さを推定可能。
- 一定の手順により客観的な強度評価が行える。
- 実際の中心気圧等とはずれがあることもあるため、補助的な手法とされることが多い。
※1:Tナンバー(T値)
「Tナンバー(T値)」とは、ドボラック法において台風の強さを表すための数値指標です。
雲の構造や形から「クラウドパターン」を評価し、そのパターンに応じてT1.0〜T8.0までの数値が割り当てられます。数値が大きいほど台風が強いことを意味し、例えば…
- T1.0〜T2.5:弱い熱帯低気圧
- T3.0〜T4.5:台風の初期〜中等度の強さ
- T5.0以上:非常に強い台風
このTナンバーに対応して、中心気圧や最大風速が推定される仕組みです。
T数から中心気圧・最大風速を推定
ドボラック法で算出される「T数」は、熱帯低気圧の現在の強度を示す0.0から8.0までの数値です。このT数と中心気圧・最大風速の間には、以下のような経験的な対応関係があります。
| T数 | 中心気圧(hPa)推定値 | 最大風速(ノット)推定値 |
| T1.0 | 約1000 | 約25 |
| T2.0 | 約990 | 約30 |
| T3.0 | 約970 | 約45 |
| T4.0 | 約940 | 約65 |
| T5.0 | 約910 | 約90 |
| T6.0 | 約890 | 約115 |
| T7.0 | 約870 | 約140 |
| T8.0 | 約850 | 約160 |
※上記は一例であり、機関や地域によって対応表が若干異なる場合があります。
このように、気象衛星画像から得られる視覚的な情報を基に、台風の勢力を数値で表し、そこから中心気圧や最大風速を推定することができるのです。
台風の中心気圧の測り方
強度推定の主要な概念とステップ
- T数(Tropical Number)
- 衛星画像の解析から得られる熱帯低気圧の強度を表す指数で、T1.0からT8.0まで0.5刻みの15段階に分けられます。
- 数字が大きいほど強度が強く、T1.0は熱帯低気圧に達する約1.5日前、T8.0は観測され得る最強のT数とされます。
- Dvorak(1975)によると、全熱帯低気圧の70%が1.0T/dayの割合で発達・衰弱しました。
- T数の1日の変化量は、標準で1.0、急な場合は1.5、ゆっくりした場合は0.5と設定されています。
- T数は、雲パターンを計測して得られるDT数(Data T数)、過去のT数の変化量から推定するMET数(Model Expected T数)、雲パターンモデル図と比較して得るPT数(Pattern T数)のいずれかから決定されます。
- CI数(Current Intensity Number)
- T数を調整して得られる値で、実際の熱帯低気圧の強度(最大風速、最低海面気圧)に対応します。
- 発達期はT数とCI数は等しいですが、衰弱期は雲パターンが強度に先行して衰弱するため、T数の減少よりも強度の低下を遅らせるように調整されます。通常、T数が減少し始めてから12時間後にCI数が減少します。
- 北西太平洋におけるCI数と最大風速・最低海面気圧の関係は、木場ほか(1990)によるテーブルで示されています。
雲パターンの分類と解析
ドボラック法では、熱帯低気圧の雲パターンを以下の典型的なタイプに分類し、それぞれ計測方法が異なります。
- 湾曲したバンド(Curved Band)パターン:中心に向かって巻く雲の帯。T数の増加とともに雲バンドの長さが伸びます。特に発生・発達期に重要なパターンです。
- CDO(Central Dense Overcast: 中心を取り巻くほぼ円形の濃密な雲域)パターン:発達した熱帯低気圧に見られる、中心を取り巻く円形の濃密な雲域。
- シヤー(Shear)パターン:下層雲列によって決定される熱帯低気圧の中心が濃密な雲域とずれているパターン。
- 眼(Eye)パターン:CDOの中央に現れる、雲がない円形の領域。
その他の重要な考慮事項
- Dvorak法の種類: 可視画像を用いるVIS法と、赤外強調画像を用いるEIR法があります。
気象衛星センターでは、より客観的なEIR法で強度推定を行っています。 - T数の時間変化の制限: 雲パターンの短周期変化(対流雲の日変化など)によるT数の急変を抑えるため、1日のT数変化量に制限を加えています。
- 上陸時のCI数の調整: オリジナルのドボラック法は上陸時の急激な強度低下を考慮していなかったため、フィリピンに上陸した台風の解析に基づいて、上陸時のCI数決定規則にタイムラグの適用除外や減少量の調整が加えられています。
中心気圧の測り方をもっとわかりやすく!
ドボラック法は、主に以下のステップで台風の強度を推定し、そこから中心気圧を導き出します。
1.台風の中心位置の特定
まず、衛星画像から台風の回転の中心(雲の渦の中心)を特定します。これは、スパイラル状の雲バンドの曲率や、明瞭な目があればその中心を見つけることで行われます。
2.雲パターンの分類とTナンバーの割り当て
気象予報官(または自動解析システム)は、衛星画像に映る台風の雲パターンを詳細に分析し、あらかじめ用意された様々な典型的な雲パターンと比較します。
主なパターンには以下のようなものがあります。
- カーブバンドパターン: 中心に向かって巻いている雲の帯。
- セントラル・デンス・オーバーキャスト(CDO): 中心付近の円形に組織化された濃密な雲域。
- 目(Eye): CDOの中央に現れる、雲がない円形の領域。
- シアーパターン: 環境場の風の鉛直シアーによって雲が中心からずれているパターン。
これらの雲パターン、その組織化の度合い、大きさ、形状、雲頂の温度(赤外画像で判断)などに基づいて、台風の強度を示す「Tナンバー(Tropical Number)」という値を割り当てます。
Tナンバーは通常1.0から8.0までの0.5刻みの値で、数字が大きいほど台風の強度が高いことを示します。
3.TナンバーからCIナンバー(Current Intensity Number)の算出
Tナンバーは観測された雲パターンから直接導かれる「客観的な値」です。
しかし、台風の強度は急激に変化することもあれば、安定して推移することもあります。
そこで、過去24時間の強度の変化傾向や、現在のTナンバーを考慮して、「CIナンバー(Current Intensity Number)」を決定します。
CIナンバーは、Tナンバーとほぼ同じ値になることが多いですが、衰弱期の台風などではTナンバーと異なる場合があります。
4.CIナンバーから最大風速と中心気圧への変換
最終的に決定されたCIナンバーは、あらかじめ統計的に求められたCIナンバーと最大風速・中心気圧の関係式(テーブル)に当てはめられます。
例えば、CIナンバーが特定の値であれば、最大風速は何ノット、中心気圧は何ヘクトパスカル、という対応表があります。
この関係式は、地域(北西太平洋、大西洋など)や時代によって微調整されることがあります。

一般向けに、とてもわかりやすい動画があったのでご紹介します。
ドボラック法の精度と誤差
■ 精度(長所)
- 気象衛星画像からリアルタイムで広範囲の台風を監視できる。
- 航空機観測が困難な地域(日本周辺など)でも中心気圧や風速を推定できる。
- 熟練者による解析では、比較的一貫性のある評価が可能。
■ 誤差(限界と短所)
- 中心気圧の誤差はおおよそ±10〜20hPa程度が一般的。
- 特に「眼」が不明瞭な未発達な台風や、衰弱期には精度が落ちやすい。
- T番号の主観的判断に依存する部分が大きく、解析者間で差が出ることも。
眼のサイズ・雲の対称性・巻き込みの見た目など、視覚的評価が中心のため、構造が複雑な場合や高緯度での解析には不向きなことがあります。
※補足
最近では、自動ドボラック法(ADT)など、客観的なアルゴリズムを使った解析も進んでおり、主観的誤差を減らす工夫もされています。
台風の強さと中心気圧の目安
気象庁では、台風の「強さ」を最大風速(10分間平均)に基づいて分類しますが、
中心気圧にもある程度の目安があります。
| 強さの区分 | 最大風速(10分平均) | 中心気圧の目安(参考) |
|---|---|---|
| 強い台風 | 33~43m/s | 約 960~945hPa |
| 非常に強い台風 | 44~53m/s | 約 945~930hPa |
| 猛烈な台風 | 54m/s以上 | 930hPa未満 |
注意点
- 実際の中心気圧は一律ではなく、台風の構造や大きさによっても変動します。
- 「強さの定義」は風速基準であり、気圧はあくまで目安であることを押さえておきましょう。
さいごに
ドボラック法は、気象予報士にとって、衛星画像から熱帯低気圧の強度を読み解くための必須の知識です。
その確立された手法と限界を理解することは、試験対策はもちろんのこと、実際の予報業務における正確な情報判断に直結します。
日々進化する気象観測・解析技術の中で、ドボラック法の本質を捉え、他の情報源と統合する能力が、今後の予報士に一層求められるでしょう。
参考資料
「気象予報士の資格は取りたいけど、どのように勉強すれば良いのかわからない」
「テキストを買ってみたけれど、わからないことだらけ…」
「一人で受験勉強をする自信がない」
などなど、一人で悩んでいませんか?
当講座では、この記事で解説したような専門的な内容も、初学者の方が基礎から着実に理解できるようカリキュラムを組んでいます。
AIチューターが即座に疑問を解消し、担当講師がマンツーマンで、あなたの『わからない』を徹底的にサポート。
勉強内容だけでなく、あなたに最適な学習計画も一緒に考え、独学では難しい最新の予報技術も効率的に習得できます。
今すぐ、気象予報士合格への第一歩を踏み出しませんか?
▶︎【合格ロードマップ公開!】気象予報士アカデミーで学ぶ最短合格への3ステップ
LINEで友達登録すると、3分でわかる気象予報士合格ポイント動画をプレゼント!
マンツーマンの受講相談で、あなたの疑問や不安を解消しましょう!!!
\ 講座へのご質問はお気軽に! /