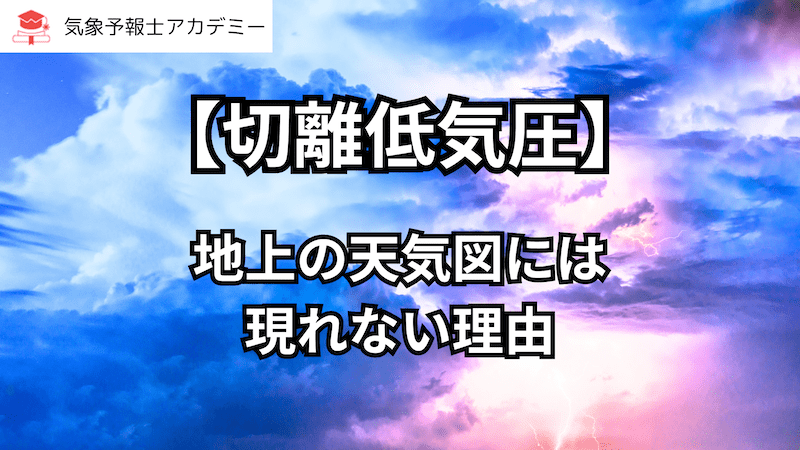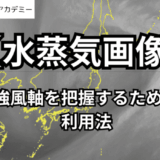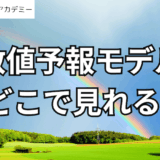またまた、受講生の方から質問をいただきました。

切離低気圧は地上の天気図には現れないのはなぜでしょうか?
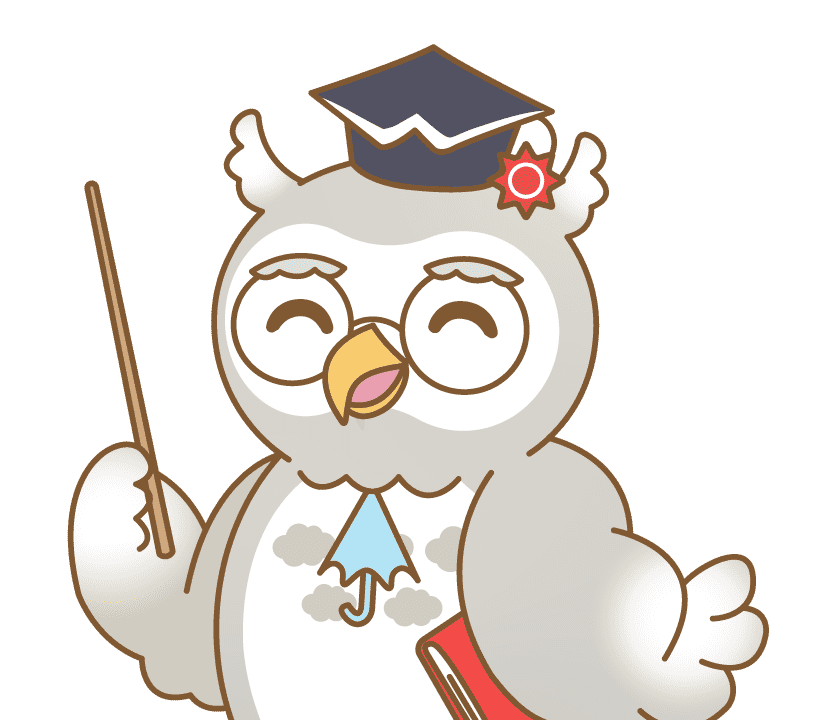
それは切離低気圧が上空の現象だからですね。
「上空に寒気があるため、大気の状態が不安定です」――天気予報でこんな言葉を聞いたことはありませんか?
実は、この「上空の寒気」の正体こそ、しばしば予測しにくい局地的な大雨や雷雨をもたらす「切離低気圧」の仕業かもしれません。
地上天気図にははっきりと現れにくく、まるで空に隠れた「冷たいいたずらっ子」のような存在。
この記事では、そんな切離低気圧の不思議なメカニズムと、それが私たちの天気にどう影響するのかを、わかりやすく解説していきます。
※この記事は、当講座に在籍する気象予報士が監修しております。
そもそも切離低気圧とは?

切離低気圧は、上空の大きな空気の流れから切り離された、冷たい空気の渦のことです。
空には、いつも目に見えない大きな空気の流れがあります。
特に上空には、地球をぐるぐる回る速い空気の流れがあり、これを「偏西風(へんせいふう)」と呼びます。
ジェット機がこの流れに乗ると早く飛べる、なんて話を聞いたことがあるかもしれませんね。
この偏西風は、いつもまっすぐ流れているわけではなく、蛇のようにくねくねと波打つことがあります。
「切離低気圧」はその名の通り、偏西風の波が大きく蛇行したときに、その波の一部がまるで本流から「切り離されて」、ぽつんと取り残されてしまうことから、そう呼ばれています。
例えるなら、大きな川の流れ(偏西風)から、泡の塊(冷たい空気)がポコッと離れて、静かに流れから外れたところに漂っているようなイメージです。
そして、この「切り離された泡の塊」の真ん中には、冷たい空気の渦があります。
だから、「寒冷渦(かんれいうず)」や「寒冷低気圧」と呼ばれることもあります。
切離低気圧の特徴って?

切離低気圧は上空の現象がメインです。
この切離低気圧は、主に地上から5,000メートルくらいの、かなり高い空で起こっている現象です。
また、偏西風の本流から切り離されているため、まるで迷子になったかのように、あまり速く動きません。
ひどい時には、同じ場所に何日も居座ってしまうことも・・・。
さて、この切離低気圧の中心には冷たい空気があるのですが、この冷たい空気が下の比較的暖かい空気の上にどっしり居座ることで、大気の「不安定」な状態が続きます。
大気が「不安定」になると、雲がモクモクと育ちやすくなります。
こんなときにできやすい雲は、モクモクと上に伸びる「積乱雲」。
その結果、同じ場所で何日も「にわか雨」や「雷雨」が続いたり、大雨になったり、時には雹(ひょう)が降ったりすることもあるのです。
まるで、冷たいいたずらっ子が居座って、ずっと雨を降らせているみたいですね。
日本では、特に梅雨の終わり頃から夏にかけてや、秋雨の時期にこの切離低気圧が現れることがあります。
この時期の切離低気圧は、ジメジメとした不安定な天気が続く原因の一つにもなるのです。
切離低気圧が地上天気図で現れにくい理由

「地上に対応する気圧の収束や温度傾度が小さいため、地上の気圧場に影響を及ぼしにくい」ことが本質です。
切離低気圧が地上天気図に現れにくい理由の一つとして、「中心に寒気を持っていること」は間接的に関係していますが、それだけが直接の理由ではありません。
もう少し詳しく見ていきましょう。
地上に現れにくい本当の理由
切離低気圧の最大の特徴は、それが「上空の現象」であることです。
特に高度5000mくらいの対流圏中層から上層に、冷たい空気の塊(寒気核)が孤立して存在しています。
この「中心に寒気を持っている」という事実が、地上天気図に現れにくくなる要因とどうつながるかというと、以下のような理由が考えられます。
「温度風の関係」による影響
気象学には「温度風の関係」という重要な概念があります。
これは、上空の風の強さが、水平方向の温度分布と関係しているというものです。
暖かい空気の塊(高気圧)は上空に行くほど風が弱まり、冷たい空気の塊(低気圧)は上空に行くほど風が強くなる傾向があります。
切離低気圧は上空に寒気核を持つため、上空では非常に強い低気圧性の循環(風が反時計回りに吹く渦)を持つことができます。
しかし、その下層(地上付近)では、この寒気核が地上の空気と直接的に結びついていない場合が多いです。
つまり、上空は強い寒気と渦があるけれど、それが地上の気圧の低下に直接つながりにくいのです。
温帯低気圧は発生時から、下層から上層まで連動して形成されている(温度風も連動している)のに対し、切離低気圧は上層から発生した渦です。
だから地上付近まで渦の力が伝わらず、温度風は連動していないことが多く、地上付近で不明瞭な場合が多いのです。
暖気の移流が少ない(またはない)
一般的な温帯低気圧が発達するためには、低気圧の前面で暖かい空気が活発に流入し(暖気移流)、その暖かい空気が上昇することで、低気圧の渦が地上まで発達していきます。
また、この暖気と寒気のぶつかり合いが前線を作り、地上天気図に明瞭に描かれます。
しかし、切離低気圧は偏西風の本流から切り離された寒気の塊であり、周囲から活発な暖気の供給を受けにくいという特徴があります。
暖気の供給が少ないと、地上の気圧の低下を強めるメカニズムが働きにくく、結果として地上には弱い気圧の谷や、不明瞭な低気圧としてしか現れないことが多いのです。
大気の「安定度」との関係
上空に冷たい空気(寒気核)があると、その下の比較的暖かい空気との間で温度差が生じ、大気が不安定になりやすくなります。
これにより積乱雲が発達し、雷雨や局地的な大雨をもたらします。
しかし、この不安定は大気全体の気圧を大きく下げることには直接結びつきません。むしろ、局地的な対流活動(上昇気流と下降気流)として現れるため、広範囲にわたる「低気圧の渦」としては認識されにくいのです。
まとめ
「中心に寒気を持っている」ことは、切離低気圧が上空で発達する主要な理由であり、それが地上との結びつきが弱いこと(暖気の移流が少ないことなど)と組み合わさって、地上天気図に明瞭に現れにくくなると言えます。
つまり、寒気を持っていること自体が地上天気図に現れにくい直接の理由というよりは、その寒気が上空に孤立して存在し、温帯低気圧のような地上の暖気との活発な相互作用が少ないことが、地上天気図で判別しにくい主要な理由、ということです。
「気象予報士の資格は取りたいけど、どのように勉強すれば良いのかわからない」
「テキストを買ってみたけれど、わからないことだらけ…」
「一人で受験勉強をする自信がない」
などなど、一人で悩んでいませんか?
当講座では、この記事で解説したような専門的な内容も、初学者の方が基礎から着実に理解できるようカリキュラムを組んでいます。
AIチューターが即座に疑問を解消し、担当講師がマンツーマンで、あなたの『わからない』を徹底的にサポート。
勉強内容だけでなく、あなたに最適な学習計画も一緒に考え、独学では難しい最新の予報技術も効率的に習得できます。
今すぐ、気象予報士合格への第一歩を踏み出しませんか?
▶︎【合格ロードマップ公開!】気象予報士アカデミーで学ぶ最短合格への3ステップ
LINEで友達登録すると、3分でわかる気象予報士合格ポイント動画をプレゼント!
マンツーマンの受講相談で、あなたの疑問や不安を解消しましょう!!!
\ 講座へのご質問はお気軽に! /