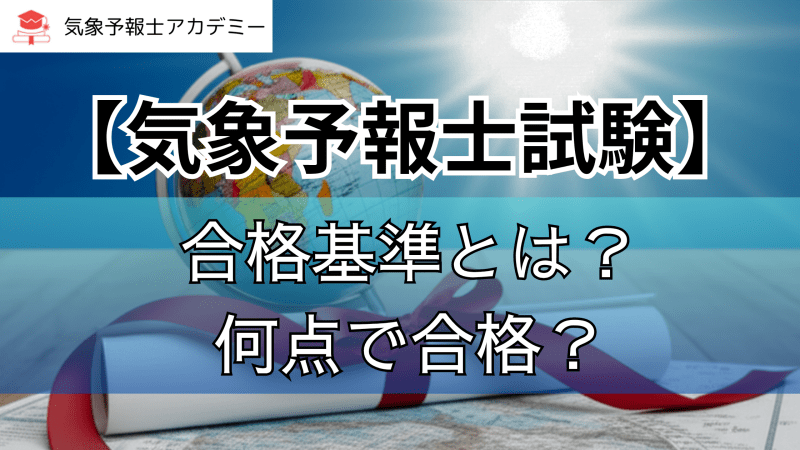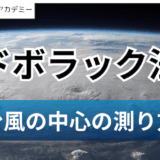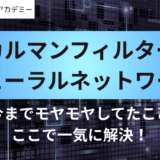気象予報士試験は、複雑な気象現象を理解し、正確な予報を行うための専門知識を問われる国家資格です。
そのため、その合格基準は厳格に定められています。
ここでは、気象予報士試験の合格基準について、具体的な点数を含めて詳しく解説します。
気象予報士試験の構成
気象予報士試験は、学科試験と実技試験の2部構成となっています。
- 学科試験: 気象業務に関する専門知識が問われます。多肢選択式で、一般知識と専門知識に分かれています。
- 実技試験: 気象図の読解や記述など、実際の予報業務に即した能力が問われます。記述式が中心となります。
合格基準の基本的な考え方
気象予報士試験の合格基準は、一律の「合格点」が設定されているわけではありません。
試験の難易度によって変動する「相対評価」と、各科目において一定のレベルに達しているかを見る「足切り基準(基準点)」の組み合わせで判断されます。
学科試験の合格基準
学科試験は、以下の2つの条件を両方満たすことで合格となります。
- 一般知識および専門知識の合計点で、概ね70%以上の正答率
- 各科目(一般知識・専門知識)において、概ね50%以上の正答率
つまり、例えば合計点が70%を超えていても、どちらかの科目が50%を下回っていた場合は不合格となります。これは、気象予報士として最低限必要な知識が偏りなく身についているかを確認するためです。
【注意点】
これは「合格点の目安」であり、毎回の試験の難易度に応じて調整される可能性があります(相対評価的な面もあり)。
したがって、「70%で必ず合格」というわけではありません。
実技試験の合格基準
実技試験も、学科試験と同様に以下の2つの条件を両方満たすことで合格となります。
- 総得点で、概ね70%以上の正答率
- 問題ごとに設定された足切り基準(基準点)を満たしていること
実技試験は記述式が多いため、部分点も考慮されます。
また、特定の重要な項目については、たとえ全体の点数が高くても、その項目の理解が不足していると判断された場合は不合格となる可能性があります。
これは、実際の予報業務において致命的な誤りを防ぐためと考えられます。
合格点の具体的な目安と注意点
上記のように、気象予報士試験の合格基準は「概ね〇〇%」という表現が使われています。これは、試験回ごとの難易度によって合格ラインが調整されるためです。
しかし、一般的には以下の点数が合格の目安とされています。
- 学科試験:
- 一般知識・専門知識ともに各15問程度出題され、それぞれ8~9問以上(約50%以上)の正答。
- 合計で21~22問以上(約70%以上)の正答。
- 実技試験:
- 総得点で70%以上。
注意点として、これらの点数はあくまで目安であり、公式に発表されている固定の合格点ではありません。 難易度の高い回では合格基準点が下がることもあれば、易しい回では上がることもあります。
合格発表と試験結果
試験結果は、試験実施後およそ1ヶ月〜2ヶ月後に、気象業務支援センターのウェブサイトや郵送で通知されます。
合格者には合格証が交付されます。
まとめ
気象予報士試験の合格基準は、学科試験と実技試験それぞれで「概ね70%以上の正答率」と「各科目(問題)での足切り基準」という二重の条件を満たす必要があります。
決して簡単な試験ではありませんが、しっかりと対策を立て、幅広い知識と実践的な能力を身につけることが合格への鍵となります。
「気象予報士の資格は取りたいけど、どのように勉強すれば良いのかわからない」
「テキストを買ってみたけれど、わからないことだらけ…」
「一人で受験勉強をする自信がない」
などなど、一人で悩んでいませんか?
気象予報士アカデミーでは、LINEでの受講相談を受け付けております。
友達登録していただいた方には、3分でわかる気象予報士合格ポイント動画をプレゼント!
ぜひご登録ください。
\ 講座へのご質問はお気軽に! /