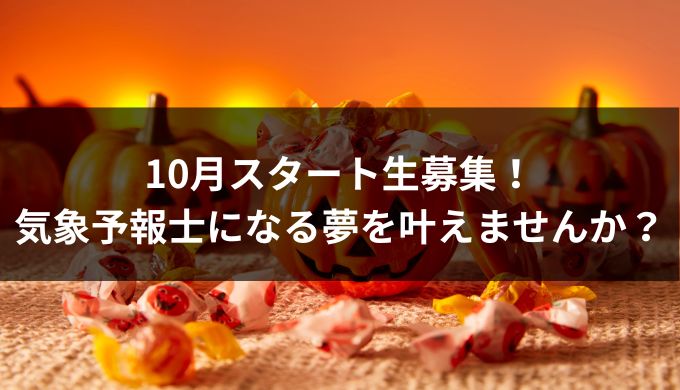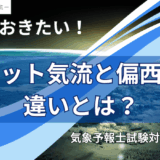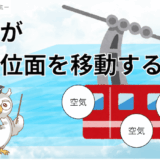10月から気象予報士試験の勉強を始める方へ。気象予報士講座を5年運営し、多くの合格者を輩出した経験をもとに、月ごとの学習スケジュールを徹底解説。未経験からでも合格可能な最短ルートと、合格後に活躍するための道筋をご紹介します。
10月スタートで翌年8月合格を目指そう!
気象予報士試験は年に2回、1月と8月に実施されます。
それぞれ、一番最後の週に実施されることが多いので、次の1月試験までは実質4か月。
| 試験月 | 試験日程 |
|---|---|
| 1月 | 毎年1月の最終週もしくはその前の日曜日 |
| 8月 | 毎年8月の最終週もしくはその前の日曜日 |
「10月から始めて間に合うの?」という疑問を持つ方も多いですが、10月スタートであれば、1月試験で学科のクリアは十分に目指せます!
約10か月間の学習で基礎から応用・実技まで段階的に積み重ねれば、未経験からでも現実的に合格を目指すことができます。
そして、次の8月試験で合格を目指す!!
でも、少し注意点があります。
10月スタートの注意点
気象予報士試験対策の講座を運営していて、一番入校してくる人が多いのは9月です。
夏の暑さが落ち着いたころ、また、8月試験が終わって独学で難しいと思った方などが多くスタートされます。
ですので、10月スタートはその9月スタートの方に比べると1か月ほど出遅れていることになります!
また、次の1月試験まで4か月あるとはいえ、4か月というのは学科一般・学科専門の2科目を狙うには、相当な勉強量の確保と「勉強するぞ!」という覚悟が必要になると考えます。
そのため、学科一般に絞るのか、学科専門に絞るのか、戦略を立てて勉強を進める必要があると思います。
10月からの学習ロードマップ(勉強スケジュール)
1月試験で2科目合格を目指す!という方はこちらの「9月から始めるといつ合格できる?気象予報士試験のリアルな学習スケジュール」を参考に、9月スタートの人に追いつくようにスケジュールを立ててみてください。
今回は学科一般のみのクリアを目指すケースで考えます。
| 時期 | 学習目標 |
|---|---|
| 10月 | 学科一般の基礎インプット(気圧・前線・放射・大気熱力学 など)を一巡する |
| 11月 | 学科一般の2巡目を進めながら、学科専門で学科一般の知識とリンクができるもの(台風や気象災害などのパート)にも目を通す |
| 12月 | 一般の実践知識のインプット |
| 12月 | 過去問で実力チェック(最低3年分)。間違えた問題や頻出問題を解いて弱点補強。 |
| 1月 | 過去問を本番通りに実施し、解答精度(速さ×正確さ)の強化。 |
| 1月 | 1月試験を受験(学科一般のクリアを目指す) |
| 2月 | 学科専門の基礎インプット(観測・予報・気象災害 など)を一巡する |
| 3~4月 | 学科専門の二巡目に加えて、実技の基礎インプット(台風や梅雨などの型を習得) |
| 5~6月 | 実技の実践知識のインプット(過去問で良問と言われる問題を解く) |
| 7月 | 過去問で実力チェック(第一弾として3年分くらい)。間違えた問題や頻出問題を解いて弱点補強。 |
| 8月 | 過去問を本番通りに実施し、解答精度(速さ×正確さ)の強化。 |
| 8月 | 8月試験を受験 |
10月から勉強を始めた場合に確保できる勉強時間
気象予報士試験に合格するためには、独学なら約1000時間、講座を活用すれば約500時間の学習が目安とされています。
では、10月から勉強を始めた場合、1月試験までにどのくらいの勉強時間を確保できるのでしょうか。
平日は通勤・帰宅後に2時間、週末はまとまった時間を使って3時間学習すると、1週間で合計16時間の勉強時間を積み上げられます。
- 平日:2時間(通勤・帰宅後の時間を活用)
- 週末:3時間(まとまった勉強時間を確保)
👉 合計すると 1週間で16時間 勉強できます。
このペースを維持すると、
- 1か月:約64時間
- 10か月(10月〜翌年7月):約640時間
- 直前期(8月を含めると+60時間程度)
つまり、10月からスタートすれば約700時間前後の勉強時間を確保できます。
これは、講座利用の目安500時間を大きく超える数字で、十分に合格圏内に到達できる計算です。
10月に勉強をスタートするメリット
10月から勉強を始めれば、翌年8月の試験合格が十分に狙えます。
- 10か月の学習期間を確保できる
- 年内に基礎を終えられるため、年明けから応用学習に集中できる
- 仲間と一緒に始めるためモチベーションを保ちやすい
また、気象予報士試験は 8月試験 → 10月合格発表 という流れになっています。
10月に合格となると、翌春に向けて、資格を取得したばかりのフレッシュな実績を武器に、気象会社や放送局、防災関連企業などへの就職・転職活動を有利に進めることが可能です。
つまり、10月から始める学習は「合格」だけでなく「キャリアスタート」に直結する最適な選択といえるでしょう。
これが11月になると、1月に学科1科目のクリアを目指すとなると、かなり勉強を確保しなければなりません。
確実に1月試験で学科をクリアするために
確実に1月試験に学科をクリアするためには以下のポイントを抑えましょう。
戦略を立てて勉強スケジュールを考える
10月から勉強を始める場合、次の1月試験まではわずか約4カ月しかありません。最初からすべてを網羅しようとするのではなく、「学科一般」か「学科専門」のどちらかに絞って確実にクリアする戦略をとることが重要です。
そして、多くの通信教育では、テキストの疑問点を質問することはできますが、「勉強方法」や「スケジュールの立て方」まで相談できるケースは少ないのが実情です。
その点、気象予報士アカデミーでは、
- 学習内容の質問対応
- 勉強の進め方やペース配分の相談
- 学習中の不安や悩みを気軽に相談できる環境
といった形で、受講生一人ひとりに寄り添ったサポートを行っています。
気象予報士試験は、1回での完全合格が難しく、問題演習の途中で「難しすぎて投げ出したい…」と感じることも珍しくありません。
そんな時に、「わからない!」「勉強がつらい!」と正直に吐き出せる場があること自体が、学習を継続する大きな支えになります。
限られた時間で成果を出すためには、こうしたサポート環境が非常に重要です。
過去問題に早めに着手する
1月試験までの学習期間は限られています。
そのため、できるだけ早い段階から過去問題に取り組むことが重要です。
気象予報士アカデミーでは、「まずテキストを全部終えてから」ではなく、学習初期から過去問に触れることも推奨しています。
なぜなら、
- 実際の試験で出題されるレベルや傾向を早めに把握できる
- 「どんな知識を学べば解けるのか」が明確になり、効率的に学習できる
- 問題を解いた上でテキストを読むことで、理解が深まり記憶に残りやすい
といったメリットがあるからです。
特に気象予報士試験は、範囲が広く、独学では「どこから手をつけるべきか」で迷う方が多い資格です。
過去問題を早めに体験することで、「必要な知識」と「試験に出る知識」の優先度を把握しやすくなります。
気象予報士アカデミーでは通常は別料金になることが多い「過去問解説」も講座費用に含まれています。
これにより、受講生は追加費用をかけずに、最新の出題傾向を押さえながら学習を進めることができます。
「問題を解くだけ」ではなく、なぜ解けなかったのか・どの知識が足りなかったのかまで理解できるようになっているため、合格への近道となります。
2025年10月スタートした場合に受講できるリアルタイム講座紹介
気象予報士アカデミーでは、定期的にリアルタイム講座(オンラインLIVE授業)を開催しています。
2025年は、10月9日(木)までのお申し込みの場合、10月11日(土)開催の講座に参加可能です。
今回のテーマは「徹底的に低気圧!」2時間半にわたり、低気圧の構造・発達・予報に直結する知識を徹底的に解説します。
リアルタイム講座に参加することで、
- テキストでは理解しにくい部分をその場で質問できる
- 受講生同士の刺激を受けながら学習できる
- 1人では挫折しがちな学習を続けやすくなる
というメリットがあります。
10月からの学習スタートと同時に参加できるため、スタートダッシュを切るのに最適な機会です。
気象予報士アカデミーに興味をもっていただいたあなた!今ならeラーニングが体験できます!
「気象予報士アカデミーは気になるけど内容が気なる」という方はぜひ問い合わせフォームかLINEでお知らせください!
LINEの友達登録していただいた方には、3分でわかる気象予報士合格ポイント動画をプレゼント!
ぜひご登録ください。(メッセージのやり取り用なので講座の案内は一切配信しておりません!)※登録しただけでは当方に通知がこないため、質問を送ってくださいね!
個別に受講相談も承っています!ご希望の日程をお知らせください!
\ 講座へのご質問はお気軽に! /